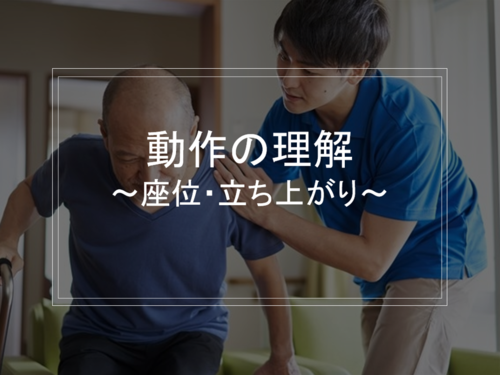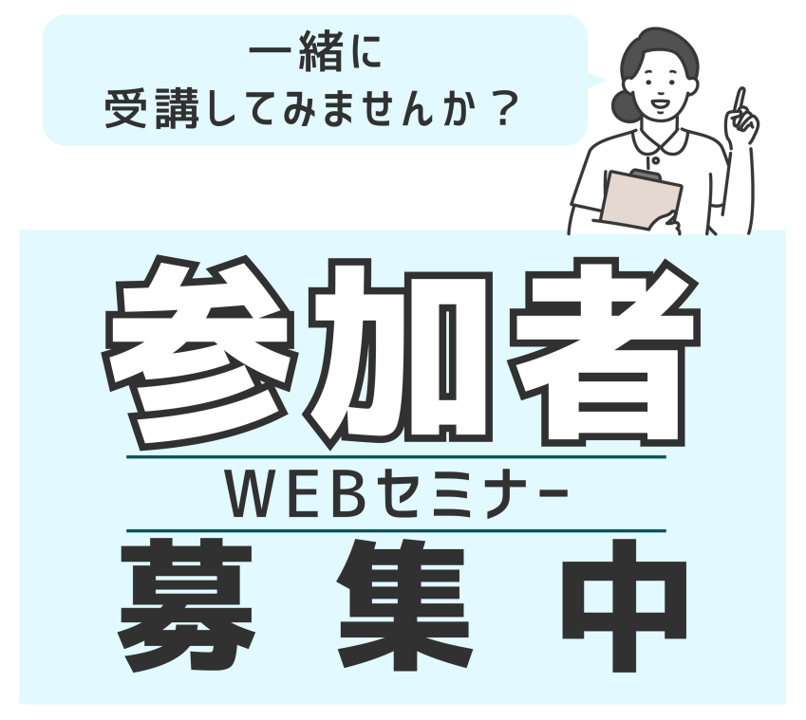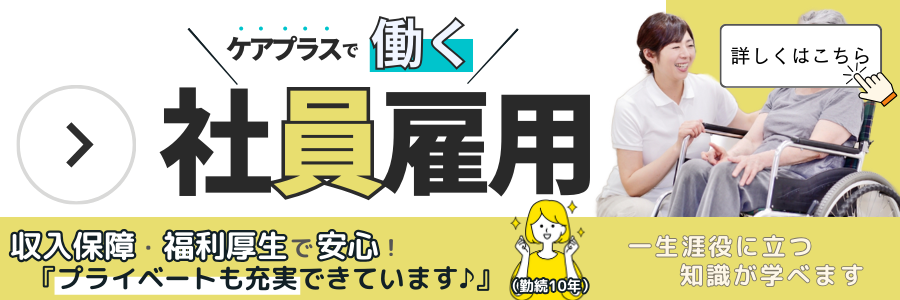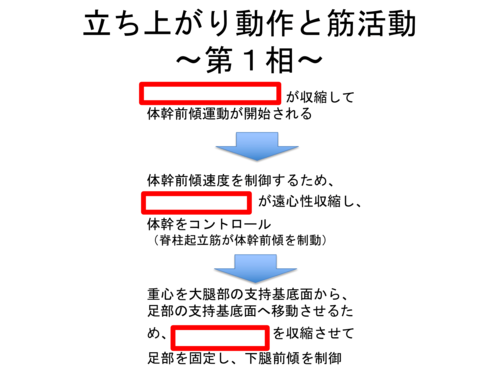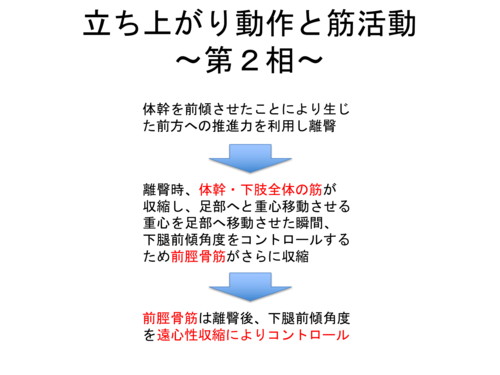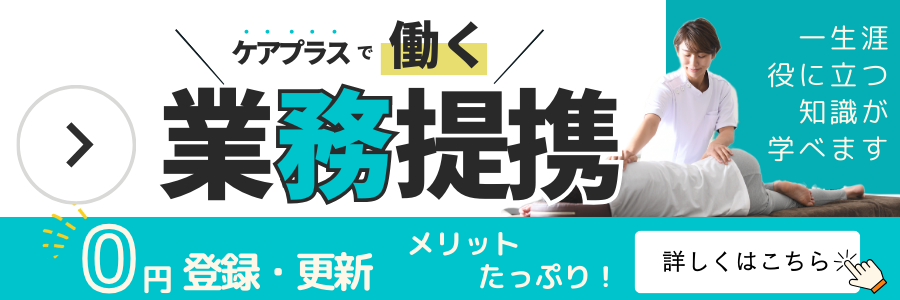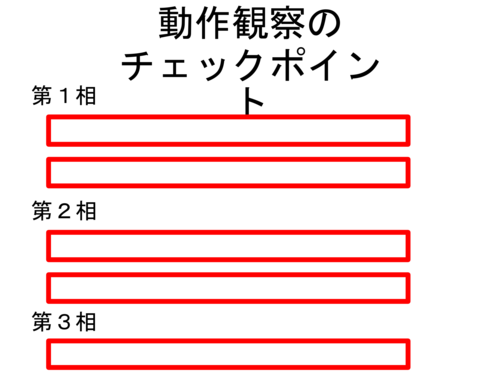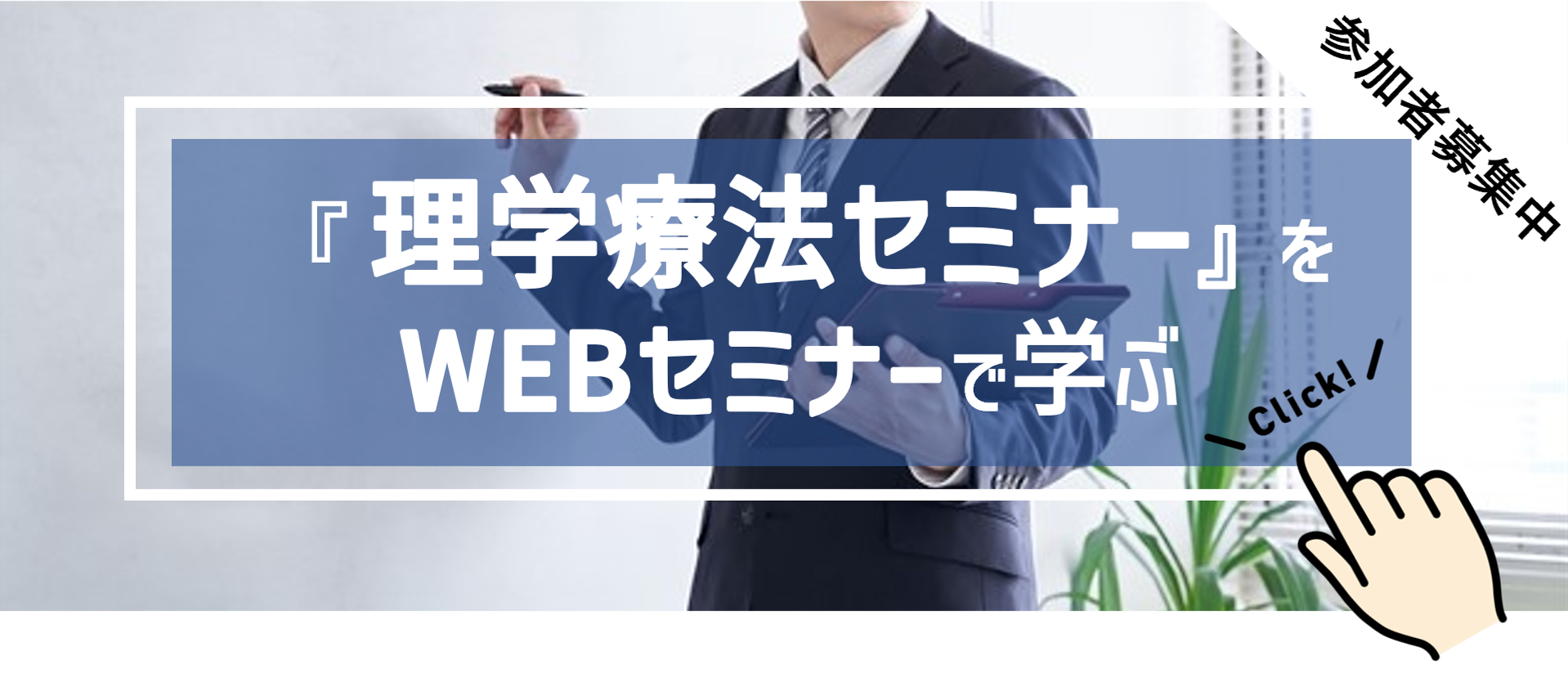20201118-04 「廃用症候群の姿勢・動作リハビリ」
セミナ―レポートをご観覧いただき、誠にありがとうございます。
今回の講義内容:「廃用症候群の姿勢・動作リハビリ」 2020年11月18日
講師:㈱ケアプラス テクニカルアドバイザー 理学療法士 Mr.T
今回も、大勢の方に参加いただき充実した会となりました。
ご参加の皆様、「理学療法WEBセミナー」を熱心に受講していただき、誠にありがとうございました。
T先生、分かり易く熱意あるご講義をありがとうございました。
セミナーの概要については以下をご参照ください。
目次
1 ADL IADL
2 座位
3 座位の重要性
4 覚醒と座位
5 覚醒と座位 2
6 覚醒と座位 3
7 拘縮と座位
8 拘縮
9 筋力と座位
10 座位のリスク
11 座位により
12 例えば
13 排泄と座位
14 排泄と座位 2
15 排泄姿勢と腹圧のメカニズム
16 食事と座位−咀嚼・嚥下メカニズム−
17 第1相:
18 第2相:
19 食事と座位−咀嚼・嚥下メカニズム− 2
20 咀嚼
21 誤嚥
22 チェックポイント〜環境設定〜
23 立ち上がり動作の相分け
24 立ち上がり動作と関節角度
25 立ち上がり動作と筋活動
26 立ち上がり動作と筋活動〜第1相〜
27 立ち上がり動作と筋活動〜第2相〜
28 立ち上がり動作と筋活動〜第3相〜
29 立ち上がりの筋活動
30 座り込みの筋活動
31 動作観察のチェックポイント
32 動作観察のチェックポイント〜第1相〜
33 動作観察のチェックポイント〜第2相〜
34 動作観察のチェックポイント〜第3相〜
35 次回予告
23 立ち上がり動作の相分け
第一相 : 端座位~前かがみ
第二相 : 前かがみ~お尻が浮く
第三相 : 伸びあがり~立位
24 立ち上がり動作と関節角度
立ち上がりに必要な関節角度は??
25 立ち上がり動作と筋活動
立ち上がり時はなに筋が活動??
26
27
28 立ち上がり動作と筋活動〜第3相〜
・抗重力伸展筋の筋力
(大殿筋・大腿四頭筋・下腿三頭筋)
・股関節・膝関節・足関節の 協調的な伸展運動
狭くなった支持基底面から重心が出ないように、
筋力と協調性に働かせて重心を真上に持ち上げる
29 立ち上がりの筋活動
関節モーメントと関節の動きが同じとき
→求心性収縮
30 座り込みの筋活動
関節モーメントと関節の動きが逆のとき
→遠心性収縮
31
32 動作観察のチェックポイント〜第1相〜
●体幹がしっかり前傾できてるか?
体幹前傾・股関節の屈曲を行うには、骨盤の前傾が重要だが、
仙骨座りだと骨盤が過度に後傾しており、
体幹前傾・股関節屈曲動作が困難となる。
よって動作実施には、背筋を伸ばし、
骨盤前傾を促す運動から介入すると効果的。
また、高齢者で仙骨座りが長期間続いているケースは
改善が難しい場合もある。
そのため、前方に支持物を置いたり、足部を後方に引いたりして、
重心が前方へ移動し易い環境を作る。
●足部は適切な位置にあるか?
足部が遠くに位置していると、離臀時に重心と膝関節軸との距離が増大するため、
大腿四頭筋の筋収縮が要求される。
考えられる原因は、足関節背屈可動域制限、
大腿四頭筋の過緊張や座位姿勢が後方重心であるため、
バランスを取るために足部を遠い位置においている可能性がある。
33 動作観察のチェックポイント〜第2相〜
●離臀ができるか??
原因として
・大殿筋や、大腿四頭筋、下腿三頭筋など抗重力伸展筋の筋力低下
・前脛骨筋の筋力低下
・体幹の前傾不足
・足部が前方に位置している
などがある
●下腿前傾ができない・維持できない
・足関節の背屈可動域制限
・下腿三頭筋の筋緊張亢進
・前脛骨筋の筋力低下
などが考えられる

34 動作観察のチェックポイント〜第3相〜
真上に向かってに重心移動ができているか?
真上に向かって重心移動するために必要要素は2つ
・大殿筋・大腿四頭筋・下腿三頭筋などの 抗重力伸展筋の「筋力」
・股関節・膝関節・足関節の「協調性」
筋力がなければ、重心を持ち上げられず、動作が遂行できなくなる。
また、筋力があっても、脳卒中片麻痺や小脳失調などで協調性障害がある場合、
膝関節などが速いタイミングで伸展しまい、後方へふらついてしまうというケースも多々ある。
35 次回予告
立位~歩行
✓立ち上がりの動作復習
✓立位の姿勢観察ポイント
✓歩行動作の観察ポイント
施術・セミナー動画観覧ご希望の方へ
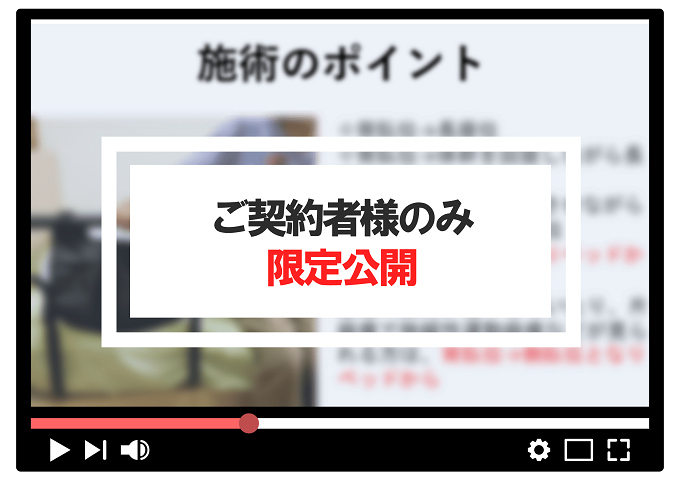
施術プログラムに関しては、セミナーで学んでいただけます。
WEBセミナーの参加や施術・セミナー動画観覧は、弊社とご契約いただいた方限定です。
●ご契約者様
過去のセミナー動画やセミナー資料を閲覧することができます。閲覧についてはご登録いただいたmailに配信された、WEBセミナーお申込みフォームよりご登録ください。
●新たに契約をご希望の方
下のバナーから契約の詳細が確認できます!

問題点の考察、機能評価、能力評価の方法、治療の方針と対策など
ケアプラスではより良質な訪問医療マッサージサービスが地域・社会に提供できるよう目指しております。